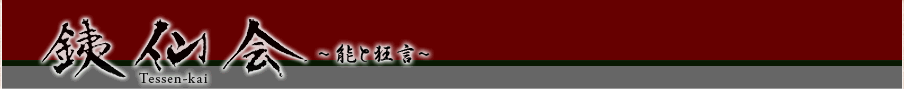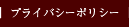関寺小町(せきでらこまち)
◆登場人物
| シテ | 老女 じつは小野小町 |
|---|---|
| 子方 | 関寺の稚児 |
| ワキ | 関寺の住職 |
| ワキツレ | 関寺の僧 【2‐3人】 |
◆場所
【1~7】
近江国 関寺(せきでら)の傍ら 老女の庵 〈現在の滋賀県大津市逢坂〉
【8~10】
近江国 関寺
概要
七夕の宵。近江国 関寺の僧たち(ワキ・ワキツレ)は、寺のほとりに住む老女が和歌の名人だと聞き及び、星の祭りに誘おうと老女の庵を訪れる。老女(シテ)は年老いた身を嘆きつつも和歌の心構えを説くが、そうするうち、上代近代の女性歌人たちについて尋ねた僧の言葉に感傷的となる。実は彼女こそ、近代の大歌人・小野小町のなれの果て。小町は、自らの正体が露見してしまったことを恥じつつ、老いの無常を嘆くのだった。
やがて夜になり、星の祭りが始まった。美しい音楽が奏される中、舞を披露する稚児(子方)。その優美な姿に、小町の心中には若かりし日の記憶が蘇り、自らも舞おうと言い出した。満天の星空の下、静かに舞を舞う小町。しかし身体の衰えには抗えず、彼女は改めて老いを嘆く。そうする内に夜は明け、小町は一人、庵へ帰ってゆくのだった。
ストーリーと舞台の流れ
1 子方・ワキ・ワキツレが登場します。
七夕。それは、暑い夏の日々もようやく過ぎ、初秋の涼やかな風が吹きはじめた七月の空の下、機織りや歌道の上達を願いつつ、星たちに供物を捧げる節句である。
その七夕の宵を迎えた、近江国 関寺の僧たち(ワキ・ワキツレ)。彼らは、今夜寺の庭で星々を祀るべく、準備を進めているところであった。聞けば、この寺のほとりに住む老女は、和歌の名手との噂。寺に仕える稚児(子方)へ歌道の手ほどきをと考えた彼らは、今年の星の祭りにかの老女を招こうと、彼女の庵に向かうところである。
2 シテが登場します。
庵の傍らに到った一行。その内へと耳を澄ませば、例の老女(シテ)の嘆息の声が聞こえてきた。「物乞いをしても一椀の食を得られぬ朝や、卑しい衣すら肌にまとうことの叶わぬ夕べ。降る雨を受けて移ろいゆく花の色——それは、世に経るままに衰えゆくわが身の果ても同じこと。若さとは一瞬のもの。春夏秋冬は毎年同じように巡れども、昔に返る日は来ない。ああ、在りし日々の恋しいこと…」。
3 ワキはシテに声をかけ、歌道の心を尋ねます。
声をかける僧。稚児たちへ和歌の指南をと願う僧に、老女は言う。「私はもはや、埋もれ木のごとき人知れぬ身。私の教えを受けずとも、心を種として言葉をつむぎ出すならば、必ずや歌道の理にも適いましょう」 歌の父母と呼ばれる、難波津・安積山の二首の歌。これらの和歌を初学の手本とすれば、都鄙を問わず貴賤をも問わず、歌を好くことは出来るはず。浜の砂よりも限りなき、言の葉の数々。それも全ては、心を種とするのだ——。
4 ワキはシテに女性歌人の話題を持ちかけ、シテは自らの正体を仄めかします。
女性の歌人は珍しい中にあって、歌道への造詣の深いこの老女。僧は、上代の衣通姫や近年の小野小町の名を挙げつつ、女性歌人の和歌を尋ねてゆく。『侘び果てて辛い私は水草のよう、誘う水あればどこへでも流れ去りたいもの』——それは、名高い小野小町の歌。僧は何気なく、老女へその話題を投げかける。
その言葉に、しんみりとした様子の老女。「これは夫の大江惟章に捨てられ、嘆きに沈んでいた頃のこと。東国へ下ってゆく文屋康秀に誘われて、私が詠んだ歌なのです…」。
5 シテは、自らの正体を明かします。
その言葉に訝る僧。もしも小町が存命ならば、その年齢はこの老女と同じほど。そう気づいてしまった僧へ、彼女は明かす。「ああ、小町とは恥ずかしいこと。人に知られぬよう過ごしてきたものを…」 小町と知られてしまった、今のこの身。今も昔の歌の如く、水草のようにどこかへ流れ去ってしまえたらと、彼女は身の零落を恥じるのだった。
6 シテは、老いの身を嘆きます(〔クセ〕)。
——歳月は移りゆき、色褪せ枯れまさるこの身。未だ世にある友はなく、亡き人ばかりが増えてゆく世の中で、いつまで無常を嘆き続けることだろう。若い頃を偲んでいた初老の時分さえ、今では慕わしく思われる。一夜の宿にも贅を尽くし、夫婦の寝室は花に彩られていた昔。しかし今や、粗末な小屋に粗末な寝床。関寺の鐘の音は人々を仏道へといざなうけれど、年寄りの耳には届かぬこと。花散りまがい、葉がはらはらと落ちてゆく折は、筆を染めて歌を書くものの、それにすら力が入らぬ、年老いたこの身の果てなのだ…。
7 ワキたちは、シテを七夕の祭りに誘い出します。
そうする内にも時刻は移る。今宵関寺で催される星の祭りに、小町を招待する僧。既に百歳にも及ぶ身、かつて公卿殿上人たちに交じって過ごした遊宴の日々からは変わり果ててしまった今の姿に、彼女は躊躇いの色を見せる。浅ましくみすぼらしい、今のこの姿。しかしそんな身ながらも、彼女は僧たちに手を引かれ、祭りの会場へと向かってゆく。
8 子方は、星に手向ける舞を舞います。
今宵は七夕。織姫・彦星、天にまたたく星たちへと捧げられる、供物の数々。音楽は美しい調べを奏で、稚児は優雅に舞の袖を翻す。盃が一座の間を廻りゆき、人々はこの心安まるひとときに、世の平穏と長久とを願うのだった。
9 シテは子方の舞に感銘を受け、自らも舞います(〔序之舞〕)。
稚児の舞い姿に、すっかり心の晴れた小町。彼女は、昔の宮中の節会を思い出す。「世には“狂人走れば不狂人も走る”というが、今の私は丁度その逆。これほどの素敵な稚児の舞に惹かれて、狂気の老いの身ながらも、一さし舞いたくなってしまったよ…」。
満天の星空の下、昔の日々を偲びつつ、静かに舞いはじめた小町。身体には老いの疲れを覚えつつも、心にはあの懐かしい日々を取り戻したように、彼女はゆったりと舞を舞う。
10 シテは、夜明けとともに庵へ帰ってゆきます。(終)
輝かしい思い出を胸に舞う小町。しかし記憶は霞んで舞の手も忘れ、身体は衰えて足元もおぼつかない。舞の袖を返すことは出来ても、昔を今に返すことは出来ぬのだ——。小町は、舞う中で改めて自覚した自らの老いに、深い嘆きを覚えるのだった。
やがて明けてゆく、初秋の短か夜。老醜の姿を見せる恥ずかしさ、もはやこれまで。…そう告げると、小町は杖にすがりつつ、衰えた足でただ一人、庵へと帰ってゆくのだった。