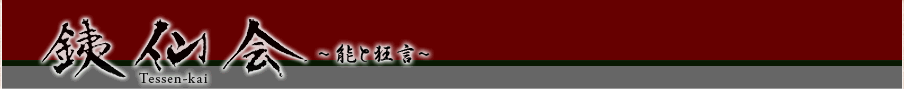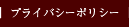遊行上人(ワキ)が従僧たち(ワキツレ)を伴って白河関にやって来ると、そこに一人の老人(前シテ)が現れ、昔の遊行上人が通った古道を教え、そこに生えている名木「朽木柳」に案内する。老人は、むかし西行がこの柳のもとに立ち寄って歌を詠んだ故事を教えると、その柳の蔭に姿を消してしまうのだった。
夜、一行が念仏を唱えていると、老柳の精(後シテ)が現れ、上人の念仏に感謝の意を述べる。老柳は、華やかなりし昔を恋い慕って柳にまつわる様々な故事を語り、弱々と舞を舞っていたが、夜明けとともに、上人に暇乞いをして消えてゆく。あとには朽木の柳だけが、そこには残っているのだった。
人跡絶えた古道のほとり。人知れず朽ち果てる運命にあった老柳は、念仏に巡り逢い救われる身となったことを喜び、華やかな昔を思い出して旧懐の舞を舞う。
| 作者 | 観世信光 |
| 場所 | 陸奥国 白河関付近 (現在の福島県白河市) |
| 季節 | 晩秋 |
| 分類 | 三番目物 老精物 |
| 前シテ | 老人 | 面:阿古父尉など 着流尉出立(老人の扮装) |
| 後シテ | 朽木の柳の精 | 面:皺尉 風折狩衣大口出立(老木の精の扮装) |
| ワキ | 遊行上人 | 大口僧出立(高貴な僧の扮装) |
| ワキツレ | 同行の聖 | 大口僧出立 |
| 間狂言 | 所の者 | 長裃出立(一般的な庶民の扮装) |
概要
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキ・ワキツレが登場します。
奥州 白河関。東路の果てに位置するこの関は、古歌にも詠まれた、都の人々のあこがれの地。いにしえ西行法師も長旅の果てに訪れた、遙かなる遠国の地であった。
その白河関にさしかかった、遊行上人(ワキ)の一行。一遍上人の教えを受け継ぐ彼らは、その教えを弘めるべく、日本中をめぐり歩いていたのであった。
秋風の吹きぬけてゆく白河関。霧の向こうに夕陽が淡い光を放つ、黄昏時のこと。
その白河関にさしかかった、遊行上人(ワキ)の一行。一遍上人の教えを受け継ぐ彼らは、その教えを弘めるべく、日本中をめぐり歩いていたのであった。
秋風の吹きぬけてゆく白河関。霧の向こうに夕陽が淡い光を放つ、黄昏時のこと。
2 前シテが声を掛けつつ登場し、ワキに道案内をします。
関を過ぎると、多くの道に分かれていた。広い道へ行こうとする一行を、一人の老人(前シテ)が呼び止める。「もうし、お上人さま。以前、前の上人が来られた時は、この道でなく昔の街道を通っておいででした。お教えしましょう、こちらへお越し下され…」。
聞けば、その道には朽木柳という名木があるという。「貴い上人のお念仏で、草木もきっと成仏が叶いましょう」 草々の乱れ茂る、人跡絶えた古道。そのほとりに柳はあった。
聞けば、その道には朽木柳という名木があるという。「貴い上人のお念仏で、草木もきっと成仏が叶いましょう」 草々の乱れ茂る、人跡絶えた古道。そのほとりに柳はあった。
3 前シテはこの柳の故事を語り、塚の中へと消え失せます(中入)。
古びた塚の上に、ひとり朽ち残った柳。そばの川も水が絶え、ひっそりと立つこの木は、蔦葛に埋もれて形も見え分かず…。それはまるで、過ぎ去った年月を物語るかのよう。
老人は語る。「昔、西行法師がこの地を訪れた折、この柳のもとで一首の歌を詠みました。その頃は傍らの小川の流れも清く、川面に映る柳の色をご賞翫になったのです…」 時を超え、今なお朽木として残り続ける柳。老人は、この木を見ては昔を懐かしむのだった。
やがて老人は、上人から念仏を授かると、そのまま塚の陰に姿を消してしまった。
老人は語る。「昔、西行法師がこの地を訪れた折、この柳のもとで一首の歌を詠みました。その頃は傍らの小川の流れも清く、川面に映る柳の色をご賞翫になったのです…」 時を超え、今なお朽木として残り続ける柳。老人は、この木を見ては昔を懐かしむのだった。
やがて老人は、上人から念仏を授かると、そのまま塚の陰に姿を消してしまった。
4 間狂言がワキに物語りをし、退場します。
そこへやって来た、この土地の男(間狂言)。彼は上人に尋ねられるまま、かつて西行がこの地で歌を詠んだときのことを語る。遊行上人たちは、荒れ果てたこの地の景色を眺め、往時を偲ぶ。
5 ワキ・ワキツレが念仏を唱えていると、塚の中から後シテが現れます。
その夜。冴えわたる月光のもと、上人はいつもの如く勤行をはじめる。
辺りに響く、念仏の声。するとその時、塚の中から声が聞こえてきた。「華やかなりし過去への執心断ちがたい、この身の上。しかし、そんな徒らに朽ちゆくこの草木の身ながらも、いま、有難い仏の道に出逢うことができたのだ…」。
忽然と現れた声の主。それは、この朽木柳の精霊(後シテ)であった。
辺りに響く、念仏の声。するとその時、塚の中から声が聞こえてきた。「華やかなりし過去への執心断ちがたい、この身の上。しかし、そんな徒らに朽ちゆくこの草木の身ながらも、いま、有難い仏の道に出逢うことができたのだ…」。
忽然と現れた声の主。それは、この朽木柳の精霊(後シテ)であった。
6 後シテはワキ・ワキツレと言葉を交わします。
白髪は乱れ、衰えた姿の彼こそ、先刻上人たちに道案内をした老人の正体であった。
柳の精は念仏の功徳を喜ぶ。「ああ、有難いこと。浄土の教えによらずば、われら心なき草木は、どうして救われることがありましょうか。念仏を唱える声とともに極楽浄土に咲いた蓮の花、それを一生大切にして絶えさせなければ、その花が迎えに来てくれるという。嬉しいことだ…」。
柳の精は念仏の功徳を喜ぶ。「ああ、有難いこと。浄土の教えによらずば、われら心なき草木は、どうして救われることがありましょうか。念仏を唱える声とともに極楽浄土に咲いた蓮の花、それを一生大切にして絶えさせなければ、その花が迎えに来てくれるという。嬉しいことだ…」。
7 後シテは柳にまつわる故事を語り舞います。
老柳の精は、昔を恋い慕いつつ、ゆったりと舞を舞いはじめる。
――古今東西に数多き、柳の徳。わが国 清水寺の音羽滝は、今なお絶えることなき、楊柳観音の霊験あらたかな名水。京都の春の盛りには、宮中では柳のもとで蹴鞠が催され、源氏物語の柏木の恋も、その蹴鞠がきっかけだった。しかし今や、そんな華やかな昔からは遠く隔たってしまった。この年老いた柳は、気力も無く弱々と、風に漂い舞うばかり…。
――古今東西に数多き、柳の徳。わが国 清水寺の音羽滝は、今なお絶えることなき、楊柳観音の霊験あらたかな名水。京都の春の盛りには、宮中では柳のもとで蹴鞠が催され、源氏物語の柏木の恋も、その蹴鞠がきっかけだった。しかし今や、そんな華やかな昔からは遠く隔たってしまった。この年老いた柳は、気力も無く弱々と、風に漂い舞うばかり…。
8 後シテは〔序之舞〕を舞い、別れを惜しみつつ消えてゆき、この能が終わります。
昔を恋いつつ、朽ちてゆくばかりであった柳。しかし今、逢い難き仏の教えにめぐり逢えた柳の精は、その喜びに舞を舞い始める。それはまるで、歌舞の菩薩の姿のよう。
やがて、鶏の声が聞こえはじめ、別れの時刻がやって来た。柳の精は上人に暇を乞うと、足元も弱々と去ってゆく。秋の風が吹き抜け、露も木の葉も散ってゆき…、
あとには朽木の柳だけが、そこには残っていたのだった。
やがて、鶏の声が聞こえはじめ、別れの時刻がやって来た。柳の精は上人に暇を乞うと、足元も弱々と去ってゆく。秋の風が吹き抜け、露も木の葉も散ってゆき…、
あとには朽木の柳だけが、そこには残っていたのだった。
みどころ
本作の作者・観世信光は、他に〈紅葉狩〉や〈船弁慶〉を作ったことでも知られています。彼の活躍した戦国時代、能を楽しむ階層も変化し、幽玄で趣ふかい能よりも華やかでスペクタクルの能のほうがもてはやされるようになりましたが、その時期に活躍していた信光の作品にも、そういった曲趣の作品が多くなりました。しかし信光晩年の作品である本作はそういったショー的な作風ではなく、世阿弥以来の幽玄を基調とする作品で、老境にあった信光の心情が反映されているのかもしれません。
本作の、老木の精が老人の姿となって現れ、閑雅な舞を舞うという趣向は、世阿弥の〈西行桜〉に強い影響を受けて作られています。
柳といえば、「道のべの朽木の柳春くればあはれ昔と忍ばれぞする」という歌がありますが、昔の華やかな日々、源氏物語に登場する柏木が女三宮に恋するきっかけともなった宮中での蹴鞠のことなどを思い出し、年老い枯淡の境地に達した身ながら昔を偲んで幽玄な舞を舞うのが、本作のみどころとなっています。柳にまつわる故実を語ってゆく〔クセ〕の中には、鞠を蹴る型(「暮れに数ある沓の音」)や飼い猫の紐を引く型(「手飼の虎の引き綱も」)などの写実的な型もあり、閑寂な曲趣の中にも華を添えています。
柳といえば、「道のべの朽木の柳春くればあはれ昔と忍ばれぞする」という歌がありますが、昔の華やかな日々、源氏物語に登場する柏木が女三宮に恋するきっかけともなった宮中での蹴鞠のことなどを思い出し、年老い枯淡の境地に達した身ながら昔を偲んで幽玄な舞を舞うのが、本作のみどころとなっています。柳にまつわる故実を語ってゆく〔クセ〕の中には、鞠を蹴る型(「暮れに数ある沓の音」)や飼い猫の紐を引く型(「手飼の虎の引き綱も」)などの写実的な型もあり、閑寂な曲趣の中にも華を添えています。
しかし一方で、この柳の精による舞は、念仏を授けられ、救済されることが決定した老木の精が、その念仏を授けてくれた遊行上人に対して見せる感謝の舞でもありました。本作のワキともなっている遊行上人とは、今も神奈川県藤沢市にのこる清浄光寺(遊行寺)の住職のことで、一遍上人の後継者として、阿弥陀仏の救済を証明するお札を配る「賦算(ふさん)」をしつつ全国を旅してまわっていました。本作では、ほんらい心をもたず、それゆえ成仏することもない植物の精が、念仏によって救われることが描かれています。後シテが登場する場面で「いたづらに朽木の柳時を得て、今ぞ御法に合竹の」と謡われますが、人跡絶えた古道で、人知れず朽ち果てる運命にあった老柳の精が、念仏の力によって救われることとなった喜びが、本作では描かれています。
昔を偲びつつ、いたずらに朽ち果てる時を待っていた老木の精。戦国時代、能の創作が終わりを迎えようとする中で到達した、閑雅な老いの世界をお楽しみ下さい。
(文:中野顕正)
(最終更新:2017年8月)