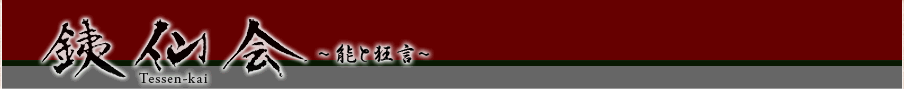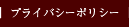◆登場人物
| 前シテ | 男 じつは妖怪・鵺の霊 |
|---|---|
| 後シテ | 妖怪・鵺の亡霊 |
| ワキ | 旅の僧 |
| アイ | 土地の男 |
◆場所
摂津国 芦屋の里 〈現在の兵庫県芦屋市〉
概要
摂津国 芦屋の里を訪れた旅の僧(ワキ)は、化け物が出ると噂される海岸の御堂に泊まる。そこへ、一人の男(前シテ)が朽ち果てた小舟に乗って現れた。男は自らを妖怪・鵺の亡魂だと明かすと、帝を悩ませながらも最後には源頼政に討たれて果てた様子を語る。男は僧に救いを求めると、再び舟に乗り、波に流されつつ消えてゆく。
その夜、僧が弔っていると、鵺の亡霊(後シテ)が真の姿を現した。鵺は、国家を傾け仏法を妨げようとして命を落とすに至った顛末を見せ、退治の功によって名を挙げた頼政の様子を語る。さらに鵺は、それにひきかえ自らの死骸は捨てられて淀川を漂い、この里で朽ちていったことを明かし、今なお闇路にさまよい続ける自らの末路を語ると、救済を願いつつ消えてゆくのだった。
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキが登場します。
摂津国 芦屋の里。瀬戸内海に面し、淀川の河口にも程近いこの里は、西国への旅の玄関口。それは、都を去りゆく者たちの眼前に広がる、外の世界への入口であった――。
その芦屋へとさしかかった、一人の僧(ワキ)。熊野参詣を遂げた彼は、次なる目的地・都を目指す旅の途上。時刻は夕暮れ時、彼はこの里で一夜を明かそうと、宿を貸してくれる里人を捜すところである。
2 ワキはアイに宿を借りようとして断られ、無人の御堂を紹介されます。
土地の男(アイ)に声を掛ける僧。ところが、彼は僧の願いに渋い顔をする。聞けば、この里で余所者を泊めることは御法度であった。彼は、海辺に建つ無人の御堂ならば泊まれるが、そこは毎晩化け物が現れるとの噂だと教える。僧はこの里の冷淡さに落胆しつつ、その御堂へと向かうのだった。
3 前シテが登場します。
御堂に腰を下ろし、ぼんやりと外を眺めていた僧。すると、一艘の小舟が、暗い海のかなたから近づいて来た。舟の中には一人の男(前シテ)。「闇路をさまよう、今のわが身。それはまるで、狭い籠の中で身動きもできぬまま、ひとり波間を漂うに同じ。魂は消え去ることすら叶わずに、今なおこの世に留まり続ける。在りし日を偲んで涙するばかりの、わが執心のなれる果てよ…」。
4 ワキは前シテと言葉を交わします。
噂に違わぬ、異様な雰囲気をたたえた男。舟は埋もれ木のごとく朽ち果て、男の風貌もそれと分からぬほどであった。奇異の思いをなす僧に、男は告げる。「もとより朽木のごとき、人に知られぬこの身。この辛い今の境遇は、嘆きを留めるに暇なく…。どうか、この心の闇を弔って下さいませ。名もなき今の身には、仏法の力だけが頼みなのです――」 彼こそ、むかし近衛帝に災いをなし、源頼政に討たれた妖怪・鵺の亡魂であった。
5 前シテは自らの正体を明かし、最期の様子を再現します(〔クセ〕)。
僧に回向を願う男。男は、自らの最期の様子を明かしはじめる。
――毎夜、内裏を覆う黒雲に、次第に重病となってゆく帝。さては妖怪の仕業かと、議論の末、警護に選ばれたのが源頼政であった。夜も更け、今夜もまた黒雲が覆う。見れば、そこには怪しき者の影。そのとき頼政が放った入魂の矢は、かの雲中の者の姿を捉えた。落ちてきた妖怪。従者の猪早太は素早く駆け寄ると、刀を以てこれを仕留める。見れば、その妖怪の頭は猿、蛇の尾に虎の手足をもった、世にも恐ろしい姿であった…。
6 前シテは消えてゆきます。(中入)
男の言葉に耳を傾けていた僧。僧は男に回心をすすめ、成仏の道へと促す。そんな僧に、男は告げる。「仏の道への入口は、一体どこにあるのでしょうか。徒らに浮沈を繰り返すばかりのこの身、こうして貴方に出逢えた今宵こそ、このご縁によって…」 その言葉を遺し、再び舟へと身をゆだねる男。舟は波間に見え隠れしつつ、次第に遠ざかってゆく。あとには、恐ろしい鵺の鳴き声だけが、辺りにこだましていたのだった。
7 アイが再登場し、ワキに鵺退治の故事を物語ります。
そこへ先刻の里人が、僧を心配して訪ねて来た。僧から化け物の正体を聞いた彼は、鵺にまつわる里の伝承を物語る。それを知った僧は、鵺の亡魂を救おうと決意する。
8 ワキが弔っていると、後シテが現れます。
やがて夜も更けた頃。打ち寄せる波は仏法の響きを奏で、空には真如の月が、澄んだ影を地表に落とす。僧の読経に添えられた、悟りの世界へと導く自然の情景。
やがて、その声に引かれ、鵺の亡魂(後シテ)が姿を現した。「土も草木も、あらゆる存在に成仏の道が開かれた世界。妖怪のこの身とて、釈迦の入滅に駆けつけた鳥獣たちと変わるところはない。私もまた、この教えを慕い、今こうして現れたのだ――」。
9 後シテは、自らの死の様子をふり返ります。
在りし日に変わらぬ、恐ろしい怪物の姿で現れた鵺。鵺は自らの死を回想し、語りはじめる。「この世界に渦巻く悪心が凝り集まり、形となって現れた私。仏法を妨げ、国家を傾けようと、帝に害をなすべく黒雲に乗ってやって来た。恐怖に怯える帝の姿に、私はますます勢いを増す。ところがあの日、思いもよらぬ頼政の矢を受け命を落としたこと、思えばこれも天罰だったのだ…」。
10 後シテは、頼政の名声と自らの末路とを語り、消えてゆきます。(終)
――後日、頼政への恩賞授与の日。初夏の時鳥が興趣を添える中、大臣が連歌を詠みかければ、頼政もそれに唱和する。文武両道の彼は、ますますその名を挙げたのだった…。
「それにひきかえ、私の亡骸は丸木舟に押し込められて流された。淀の川波に浮沈をくり返す舟。やがてこの里に漂着した私は、舟もろとも、そこで朽ちていったのだ…」 勝者と敗者とが辿った、運命の明暗。鵺は、闇路に迷うわが身を思い、救いの訪れを願い続ける。遥かなる空のかなた、月の光を仰ぎつつ、鵺は海底へと消えてゆくのだった――。