平安末期。最高権力者となった平清盛は娘 徳子を高倉天皇の后とし、彼女の産んだ安徳天皇を即位させたので、外戚となった平家は空前絶後の栄華を極めるに至った。しかし、その栄光も長くは続かなかった。清盛の死後、源氏の軍勢によって平家一門は都を追われ、安徳天皇をはじめ、一門の人々は壇ノ浦で海の藻屑と消えたのであった…。
戦後、壇ノ浦で辛くも救助された徳子は出家し、都の北 大原の地で余生を過ごしていた。
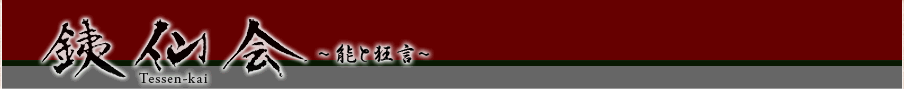


| 典拠 | 『平家物語』 |
| 作者 | 不詳(一説に、金春禅竹か) |
| 場所 | 京都の北 大原 寂光院 (現在の京都市左京区大原) |
| 季節 | 初夏 |
| 分類 | 三番目物 現在鬘物 「三夫人」の一つ(他に〈定家〉〈楊貴妃〉) |
| 前シテ | 面:若女など 尼出立(小袖)(尼僧の扮装) | |
| 後シテ | 同 | 面:若女など 尼出立(水衣)(尼僧の扮装) |
| ツレ | 面:小面など 尼出立(小袖) | |
| ツレ | 面:深井など 尼出立(小袖) | |
| ツレ | 後白河法皇 | 直面 法皇出立(出家した上皇の扮装) |
| ワキ | 風折狩衣大口出立(貴族の扮装) | |
| ワキツレ | 後白河院に仕える臣下 | 大臣出立(正装した貴族の扮装) |
| ワキツレ | 大口モギドウ出立(輿を担ぐ役人の扮装) | |
| 間狂言 | 従者 | 長裃出立(下級武士・庶民などの扮装) |
平安末期。最高権力者となった平清盛は娘 徳子を高倉天皇の后とし、彼女の産んだ安徳天皇を即位させたので、外戚となった平家は空前絶後の栄華を極めるに至った。しかし、その栄光も長くは続かなかった。清盛の死後、源氏の軍勢によって平家一門は都を追われ、安徳天皇をはじめ、一門の人々は壇ノ浦で海の藻屑と消えたのであった…。
戦後、壇ノ浦で辛くも救助された徳子は出家し、都の北 大原の地で余生を過ごしていた。
高倉帝の父・後白河院は、徳子にとっては舅に当たる。院は、今では建礼門院と呼ばれている徳子を慰問すべく、大原へ御幸(院がお出ましになること)をしようと思い立った。
御幸の準備を命じられた院の臣下(ワキツレ)は、従者(間狂言)を呼び出し、道中の整備を命じる。従者は、その旨を人々へ告知する。いよいよ、準備はととのった。
一方、大原 寂光院では、建礼門院(シテ)が、わが子の安徳天皇や平家一門の菩提を弔いつつ、ひっそりと暮らしていた。中宮であった昔の華やかな生活に引きかえ、今では大納言の局(ツレ)と阿波の内侍(ツレ)の二人だけが、女院に付き添っているのであった。
自給自足の生活。「ねえ、後ろの山で、仏さまにお供えするお花を摘んできましょう。」女院はそう言うと、大納言の局を伴い、後ろの山へと上がっていった。
ちょうどそこへ、後白河院(ツレ)の一行が、女院の慰問のためにやって来た。
大原の様子を御覧になる院。季節は初夏、寂光院には夏草が茂り、ホトトギスの鳴き声が辺りにこだまする。池の水面には桜の花びらが浮かび、過ぎ去った春の名残を留めている。その中に建つ庵室はやつれ古びた佇まいを見せ、まことに寂しげな、隠棲の地のありさま。
院に随行していた万里小路中納言(ワキ)は、庵室の留守番をしていた内侍に案内を請う。しかし女院は外出中だと言われ、一行は暫くここに逗留して女院の帰りを待つことにした。
「そこの尼御前、そなたは何者じゃ」院は、内侍に声をかける。内侍は答える。「歳月は流れ、お見忘れもごもっとも。私は、昔あなた様に寵愛されておりました信西(しんぜい)の、娘の成れる果てでございます…」 そう言うと内侍は、さめざめと涙を流すのだった。
そこへ、女院(後シテ)と局が戻ってきた。「明けても暮れても、わが子安徳天皇の面影は、片時も忘れることが出来ぬもの。花を摘むにも、私の心にあるのは、あの子と平家一門のことばかり…。」いたわしい、女院の姿。
院の一行に気づいた局は、女院に報告する。「なに、院がお出ましとな。辛い日々から離れ、この山中で閑かに暮らしていたが、院にお会いしてはまた現世への執着の心が湧き起こってしまう…」女院は、院を見て昔のことが思い出され、涙に袖を潤すのであった。
女院は院に声をかける。「これは法皇さま。この山奥で、再びお会いしましょうとは…。」
院は言う。「女院よ。噂では、そなたは生きながらにして六道輪廻の諸世界を見たというではないか。人間の身で、不思議なことよ。その様子を、語って聞かせてはくれぬか。」
女院は、語り始める。「天子の母となったこの身、それは天道の世界も同じこと。しかしそれも“天人五衰”の言葉の如く、やがては衰えゆく運命にあったのです…。」
――都を追われ、西海の波に漂う身に。飲水も底をつき、周りの水は海水ゆえ飲むことも叶わず。喉の渇きが兵士達を襲い、苦しむ様はまるで餓鬼道。ある時は荒波に揉まれ、舟は転覆せんばかりに激しく揺れる。パニックになった人々の泣き叫ぶ声は、さながら地獄道。陸に上がれば修羅道の如き源平の戦い。日夜聞こえてくる馬の足音にはノイローゼとなり、畜生道もかくやとばかり。人間道にありながら、かくも辛い日々だったのです…。
院はさらに、安徳天皇の入水の様子を尋ねる。女院は、語り始める。
――壇ノ浦の戦い。緒方三郎の裏切りで九州へも行けず、潮に遮られて退路も断たれた私達。頼みの教経・知盛は海水に入って果てた。そのとき二位の尼は「わが身は女人なりとも、敵の手には渡るまじ」と、帝を抱いて船端へ。「我を連れてどこへ行く」と尋ねる帝を、尼は諭す。「この逆賊多き国を離れ、極楽という素晴らしい国へ行くのです」と…。
――帝は東へ向かい伊勢神宮に暇乞いをすると、西方浄土へ向かって念仏を唱えられ、「今ぞ知る御裳濯川の流れには波の底にも都ありとは」という御歌を詠み、遂に水中へ入られた。私も後へ続いたが、源氏の武者たちに救助され、死に損なったのだった…。
語るも涙、聞くも涙の物語。名残は尽きず、時刻は移る。院は「もはやこれまで」と帰ってゆく。あとに残った女院は、一行を見送ると、庵の中へと戻っていったのだった。
本作は、『平家物語』の最終巻である「
「灌頂巻」は、平家琵琶の流派のひとつである
本作は、この「灌頂巻」のうち、後白河法皇の来訪を描いた「大原御幸」の段をほぼそのまま舞台化した作品となっています。
「灌頂巻」でも、本作同様、建礼門院は生きながらにして六道めぐりを経験したことを語り、また安徳天皇の入水の様子を物語ります。安徳天皇の入水に関しては、すでに『平家物語』中の別の箇所で描かれてはいるのですが、それを建礼門院の口から語りなおさせるところに、「灌頂巻」の魅力はあります。建礼門院を介して平家滅亡のさまが語られるという「灌頂巻」の趣向は、まさに“語り”の芸としての平家琵琶の神髄があらわれる場面であるといえましょう。
そして、その場面を舞台化した本作もまた、聴かせどころの多い、語りの魅力にあふれた作品となっています。本作は、舞いなども無く、動きがきわめて少ないもので、本来は舞台作品ではなく謡い物として作られたのではないかとする説もあります。それだけに、ことばによって平家滅亡のありさまを語るという「灌頂巻」の魅力を、そのまま能の世界にうつした作品であると言うことができましょう。
建礼門院の口から語られる、壇ノ浦の悲しみの記憶。その“語り”の世界を、たっぷりとお楽しみください。
(文:中野顕正)