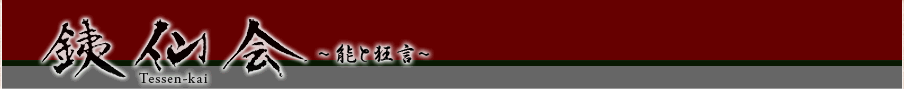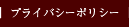女郎花(おみなめし)
◆登場人物
| 前シテ | 老人 じつは小野頼風(おののよりかぜ)の霊 |
|---|---|
| 後シテ | 小野頼風の幽霊 |
| ツレ | 小野頼風の妻の幽霊 |
| ワキ | 旅の僧 |
| アイ | 土地の男 |
◆場所
京都南郊 男山 〈現在の京都府八幡市。石清水八幡宮のある山〉
概要
女郎花の咲き乱れる男山。同地を訪れた旅の僧(ワキ)は、花を一輪手折ろうとする。それを見咎めた花守の老人(前シテ)。しかし二人の会話の中で、老人は僧を風流人として認め、特別に手折ることを許す。山上の石清水社へ参詣した二人。その別れ際、この山の女郎花の由来を尋ねる僧を、老人は山麓の古墓へ連れて行く。墓の主は、小野頼風という者とその妻。そう明かすと、老人は姿を消してしまう。実は彼こそ、頼風の霊であった。
その夜。僧が弔っていると、小野頼風(後シテ)とその妻(ツレ)の霊が現れた。ふとした誤解から、夫の心変わりを疑って命を絶った妻。その墓から咲き出たのが、例の女郎花であった。頼風が近づけば、自分を避けるように靡くこの花。その様子に悲嘆した彼は、妻の後を追って自らも川に身を投げたのだった。この生前の業により、死後もなお妄執に苦しみ続けていた頼風。そんな因果の物語を明かしつつ、夫婦は救済を願うのだった。
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキが登場します。
京都南郊 男山。それは、大阪湾へと通じる京都の玄関口。山上には皇室の宗廟・石清水八幡宮が鎮座し、この一帯は、古来人々に愛される名所であった。
その男山を訪れた、一人の僧(ワキ)。彼は故郷の九州をあとに、都を目指して旅する途上であった。この地に鎮座する石清水社こそ、故郷の宇佐神宮と一体の神。その縁を思った彼は、参詣のため、この山の山道を登ってゆく。
2 ワキは、女郎花を手折ろうとします。
見れば、野辺には女郎花が、今を盛りと咲き乱れていた。潤いを与える露の雫、あたりに奏でる虫の音までもが、花の彩りを引き立てる。この男山の女郎花といえば、古歌にも詠まれた当地の名物。ちょうど故郷への良い土産と、僧は一輪手折ろうとする。
3 前シテが声を掛けつつ登場し、花を折ることを咎めます。
その時、一人の老人(前シテ)が呼び止めた。「折ってはなりません。変わらぬ愛を契るというこの花。ましてこれは男山の…」 彼は、この野の花守であった。仏への手向けだと思って許してくれと言う僧。しかし老人は言う。「古歌にも、『手に触れては穢れてしまう。生きたままの花をこそ仏に奉ろう』と申します。また僧正遍昭は、この花に託して女性との契りを詠みました。ご出家の身であったとて、この花は叶いますまい」。
4 前シテは、ワキの風流心に免じて花を折ることを許します。
老人の挙げる古歌の数々に、すっかり気圧されてしまった僧。言葉に窮した僧は、この山道をもと来た方へ行こうとする。その時、その姿に何やら感心した様子の老人。「なるほど、古歌にはこうも言いますな。『女郎花を見ては、つらい思いのままただ行くことしか出来ぬのだ。他ならぬこの男山に、咲いているのだと思うと』と——」 その心を体現した、僧の振舞いの風流なこと。そう言うと、老人は花を折ることを許すのだった。
5 前シテは、ワキを石清水八幡宮へ案内します。
せっかくの機会と、僧を山上の八幡宮へ案内する老人。麓を見渡せば、家々は軒を連ねてひしめき合う。参道を流れる放生川の濁りこそ、濁世に現れた神の誓い。この川で行われる、“放生会”の行事の賑々しいこと。そして今日こそ、その放生会の日であった。この山を照らす澄んだ月は、神が影向された昔を偲ばせる。山々の紅葉は美しく照り映え、山は高く谷は深く、三千世界もかくやとばかり。そんな霊気を湛える聖域の中で、二人は神を伏し拝むのだった。
6 前シテはワキを古墓へ案内し、自らの正体を仄めかして姿を消します。(中入)
参詣を終え、帰ろうとする老人。そんな彼を僧は呼び止め、この男山が女郎花の名所となった由来を尋ねる。さては先刻の振舞いは、その故事を知ってのことではなかったのか。老人は落胆しつつも、僧を山麓の古墓へと連れてゆく。「この二つの墓は男塚・女塚といい、とある夫婦が葬られています。女は都の人。男はこの山に住んでいた、小野頼風という人。…いや、昔語りをするのも恥ずかしいこと。今はどうか、この跡を弔って下さいませ——」 そう告げると、老人は姿を消すのだった。
7 アイが登場し、ワキに物語りをします。
そこへやって来た、この土地の男(アイ)。男は僧に尋ねられるまま、かの小野頼風夫婦の故事を物語る。その言葉に耳を傾けていた僧は気づく。さては先刻の老人こそ、小野頼風の霊だったのか。そう確信した僧は、彼の執心を弔おうと決意する。
8 ワキが弔っていると、後シテ・ツレが出現します。
その夜。かの夫婦に思いを馳せ、経を手向ける僧。するとその声に引かれ、男(後シテ)と女(ツレ)が現れた。「人の往来も稀なこの野の中で、ひっそりと立つ古墓。これこそが、いにしえの私の墳墓なのだ。ああ懐かしい、昔の秋風。その昔に返るならば、愛しい人と一緒に…」 この男女こそ、かの小野頼風夫婦の幽霊であった。
9 後シテ・ツレは、生前のすれ違いのさまを語ります。
都に住みつつ、頼風と契りを交わしていた妻。しかし、支障あって彼の足が遠のいたのを心変わりと思い込んだ妻は、都を彷徨い出てゆく。そうして、彼の在所に程近いこの放生川へと、身を投げて果てたのだった。頼風は言う。「それを聞いた私は、急いで駆けつけました。しかしそこには、冷たくなった彼女の姿。涙ながらに遺骸を埋葬した、その跡に咲いたのこそ、かの女郎花だったのです。彼女への慕わしさに、近づこうとした私。しかしこの花は私を恨むゆえか、私を避けるように靡くのです…」。
10 後シテは、自死を決意したときの胸中を語ります(〔クセ〕)。
——それを見たとき、私は悟りました。彼女が儚く果てたのも、全ては私ゆえ。憂き世に住んだとて何になろう。彼女と同じ世界へ行くことこそ、私の真の願いなのだ。そう決意した私は、同じくこの川へと身を投げ、彼女とともに、同じ場所に葬られたのです…。
いま明かされる、“男山”の名の由来。頼風は昔の罪を懺悔し、廻向を願うのだった。
11 後シテは、死後の苦患のさまを見せ(〔カケリ〕)、消えてゆきます。(終)
「愛執ゆえに命を落とした私は、地獄に堕ちて苦しむ身となりました。鋭い刃に覆われた樹の上に、あの人の姿が見える…。身体が切り刻まれるのも構わず、愛する人の面影を追い求め続ける私。いったいどれほどの罪があって、ここまでの報いを受けるのか。私は地獄の責め苦を受けつつ、抑えられぬ自らの心を思って嘆くのです」。
思えばこれも、女郎花の因果の物語。同じ花の縁により、どうか今の弔いの力で、西方浄土の蓮台へ——。そう願いつつ、夫婦は消えてゆくのだった。