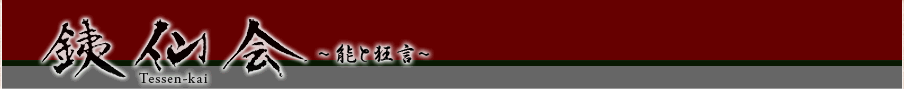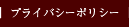小塩(おしお)
◆登場人物
| 前シテ | 花見の老人 じつは在原業平の霊 |
|---|---|
| 後シテ | 在原業平の幽霊 |
| ワキ | 花見の人 |
| ワキツレ | 同行の人 【2‐3人】 |
| アイ | 土地の男 |
◆場所
京都西郊 大原山 〈現在の京都市西京区大原野 大原野神社〉
概要
京都西郊 大原山へと花見に訪れた都人たち(ワキ・ワキツレ)。そこへ一人の老人(前シテ)が、花盛りの山中に浮かれつつやって来た。姿こそ賤しくとも、心の花は失っていないと言う老人。彼は、一行を伴って遥かに春の洛中を眺めると、「神代のことが思い出される」と呟く。それは昔、帝の后がこの地を訪れた折、供奉していた在原業平の詠んだ歌であった。そう明かすと、老人は花々の情趣に興じつつ、そのまま姿を消してしまう。
やがて――。花の蔭に休らう一行のもとへ現れた、車に乗った一人の貴人。彼こそ、在原業平の霊魂(後シテ)であった。業平は、多くの女性と契りを交わした在りし日を偲び、中でも帝の后を慕い続けた自らの思いを吐露する。この地こそ、その想いの丈を歌に詠んだ場所。業平は、往時の記憶に浸りつつ舞を舞うと、曙の空に消えてゆくのだった。
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキ・ワキツレが登場します。
洛中の春。四方の山々を見渡せば、満開の桜が咲き誇る。嶺にかかる白雲は、花の色に染められたよう。それは、人々の心も浮き立つばかりの、花の都の名に恥じぬ風情である。
そんな京都近郊の山々の中でも、西郊 大原山といえば、とりわき名高い花の名所。それは、同地に鎮座する大原野神社の神徳が、この世に跡を垂れ給うしるし。その見事な大原野の花を眺めるべく、今日もまた、都人たち(ワキ・ワキツレ)がやって来た。
2 前シテが登場します。
そこへ現れた、一人の老人(前シテ)。桜の枝をかざし持ち、まるで舞を舞うかのごとく浮かれ出た彼。老い衰えたこの身とて、花のすがたを目にすれば、鬱々とした気も晴れるというもの――。穏やかな春の日の光を受けつつ、老人は治まる御代の恵みを仰ぐ。
山々に咲き誇る花。開かぬ莟は一つとして無く、まだ散り始めもせぬ、まさに今こそ最上の時。漂うばかり花の情趣に、彼は惹かれてやって来たのだった。
3 ワキは前シテと言葉を交わします。
花見の人々の中に現れた老人。声をかける都人へ、彼は言う。「賤しき身には似合わぬ花好きと、皆々はお笑いなさるか。姿こそ山鹿のごとき身ながらも、心ばかりは花でありたいもの。その思いさえ有るならば、心の花を咲かせることも出来るはず。埋もれ木の老いの姿ながら、朽ち果てぬものはこの心。心の花は、知る人ぞ知るものですよ…」。
4 前シテは、ワキとともに四方の景色を眺めます。
奥ゆかしい老人の返答に、感心する都人たち。そんな一行の反応に満足した老人は、彼らを誘うと、景色をともに眺めようと言う。
筆舌に尽くしがたい、この花盛り。梢の間から見渡せば、霞のむこうには遠山桜、近くの里には軒端の桜。時刻は早くも黄昏どき。誰もが花の色香に惹かれ、洛中には桜の枝を折り持つ人々の数。それはあたかも、都全体が錦となったよう。「ここから見渡される花盛り、神代のことも思い出されて…」 この致景に、老人はそう呟くのだった。
5 前シテは、『伊勢物語』の故事を語ります。
老人が口にした、神代を思い出すとの言葉。それは、この地で詠まれた古歌であった。由来を明かす老人。「これは昔、帝の后がこの地へ花見に来られた折、行列に供奉していた在原業平の詠んだ歌。畏れ多くも后を慕っていた彼は、往時の契りを偲び、神話の昔に事寄せてこう詠んだのでした。時を経てなお、変わらぬものは男女の情。昔を語るこの身こそ、“昔男”に異ならぬ。ああ、古りゆくばかりのこの身の程…」。
6 前シテは、花盛りの情趣に興じつつ、姿を消します。(中入)
山賤の姿に似合わぬ、風流心ありげなこの老人。「わが心を知って下さった上は、どうかこの姿に気兼ねなく、ともに花に交わりましょう」 老いの姿ながら、若やいだその心ばえ。老人は都人たちとともに、花盛りの中へと分け入ってゆく。漂う花の風情までもが酒宴の盃に興を添え、天も花に酔うばかり。人々の面影もおぼろけになってゆく黄昏どき、老人は浮かれ戯れつつ、そのまま姿を消してしまうのだった。
7 アイが登場し、ワキに物語りをします。
そこへやって来た、この土地の男(アイ)。一行は彼を呼びとめ、この神社の由緒を尋ねる。男は語る。実はこの社の祭神・小塩明神こそ、天孫降臨に供奉した神。后に供奉していた業平は、その天孫降臨の昔に事寄せて、「神代が思い出される」と詠んだのだった。
男の言葉に、一行は気づく。あの老人は、さては在原業平の仮の姿だったのでは――。そう察した彼らは、さらなる奇蹟を見るべく、今夜はここに留まることとした。
8 ワキが待っていると後シテが現れ、二人は言葉を交わします。
その夜。満開の梢の間に、月の出を待つ頃。一行が花の下に休んでいると、忽然と花見車が現れた。車に乗るのは、一人の貴人(後シテ)。不思議に思う一行へ、彼は告げる。「雲上人の花の姿を見知らぬ者たち、驚くのも無理ないこと。その昔物語を顕わすべく、私は今、こうして現れたのだ。わが宿の花の盛りに、友を誘って歌を詠んだのも昔のこと…」 月を待とうと花の蔭に休らう彼。彼こそ、在原業平の霊魂であった。
9 後シテは、懐旧の思いを吐露しつつ舞います(〔クセ〕)。
月明かりに浮かび上がるのは、千金にも代えがたい春の宵の風情。この大原山の致景を前に、業平は、自らの心中を吐露しはじめる。
――多くの女性たちに思いを寄せ、贈り交わした歌の数々。そんな中、帝の后を慕ったために、流謫の憂き目に遭った私。忘れ得ぬものは、彼女を盗み出したあの日のこと。この思い出の地へと伸びる長い山道こそ、彼女を慕い続けるわが心の表れなのだ。“昔男”と呼ばれた私の、それは昔の物語…。
10 後シテは追憶の舞を舞い(〔序之舞〕)、そのまま消えてゆきます。(終)
「思えば、遠い昔の春のこと。しかし、ここに咲き誇る花々は、その時のことを忘れてはいまい。お后さまの参詣の、あの晴れの日のことを…」。
時刻は移り、吹きめぐる風に散りゆく花。まどろむ人々を前にして、別れを惜しみつつ、業平の姿は霞んでゆく。いま起こったことは夢なのか、それとも現実だったのか。この思い出は、曙の花にさえ残ればよい…。そう告げると、業平の姿は消えてゆくのだった。