文芸によって仏の教えを弘める“唱導”の大家・安居院法印(ワキ)が石山寺を訪れると、そこへ紫式部の霊(前シテ)が現れる。式部は、自らが生前に書いた『源氏物語』の供養を怠ったために今なお苦しんでいると明かすと、法印に供養を頼み、姿を消してしまう。
夜、法印が回向をしていると、式部の霊が在りし日の姿で現れ(後シテ)、法印の弔いに感謝して舞を舞う。式部は、無常の世を観じて救済を願う自らの思いを舞に託すと、ついに救われる身を得たことを明かし、消えてゆくのであった。
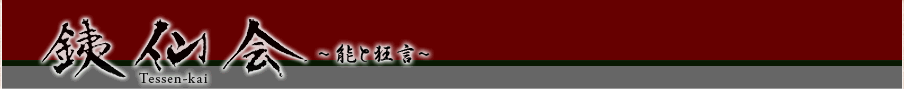


|
作者 |
未詳 |
|
場所 |
前場:近江国 石山寺門前 (現在の滋賀県大津市) |
|
後場:近江国 石山寺 |
|
|
季節 |
晩春 |
|
分類 |
三番目物 本鬘物 |
|
前シテ |
里の女 実は紫式部の霊 |
面:若女など 唐織着流女出立(一般的な女性の扮装) |
|
後シテ |
紫式部の幽霊 |
面:若女など 立烏帽子長絹女出立(舞を舞う貴族の女性の扮装) |
|
ワキ |
安居院(あぐい)法印 |
大口僧出立(格式ある僧の扮装) |
|
ワキツレ |
同伴の僧(2‐3人) |
大口僧出立 |
※このほか間狂言として所の者(長裃出立)が登場する演出もあります。
文芸によって仏の教えを弘める“唱導”の大家・安居院法印(ワキ)が石山寺を訪れると、そこへ紫式部の霊(前シテ)が現れる。式部は、自らが生前に書いた『源氏物語』の供養を怠ったために今なお苦しんでいると明かすと、法印に供養を頼み、姿を消してしまう。
夜、法印が回向をしていると、式部の霊が在りし日の姿で現れ(後シテ)、法印の弔いに感謝して舞を舞う。式部は、無常の世を観じて救済を願う自らの思いを舞に託すと、ついに救われる身を得たことを明かし、消えてゆくのであった。
春の琵琶湖。空には有明の月が残り、湖面には水煙の立つ、のどかな湖畔の風情。
そこへやって来た、安居院(あぐい)法印(ワキ)の一行。文芸によって人々を仏道へと導く“唱導(しょうどう)”の名手であった彼は、信仰する石山観音に参詣するところである。
花の盛りの都をあとに、朝霞の立ちこめる春の山路を越え、一行はこうして近江の地へとやって来たのであった。
そのとき背後から、一人の女(前シテ)が呼び止めた。「私はかつて石山寺に籠もり、源氏物語を書き上げた者。しかし完成した物語への供養を怠った科(とが)によって、今なお成仏できずにいます。どうか代わりに供養を遂げ、私を救って下さいませ…」。
この女こそ、源氏物語の作者・紫式部の霊であった。彼女は法印に回向を託すと、夕日の光の中へと消えてしまうのだった。
石山寺に参詣した一行は、かの女の言葉のままに、源氏物語の供養をはじめる。「虚構と美辞麗句とに飾り立てられた、真理に背く物語。しかしそれとても、人々を仏道へと導く方便なのだ…」 法印は物語を供養し、紫式部の菩提を弔う。
夜も更け、辺りはひっそりと静まりかえる頃。見ると、灯火の陰に一人の女性(後シテ)が立っていた。美しい顔ばせに、紫の薄衣をまとった彼女こそ、紫式部の幽霊であった。
法印の回向に感謝する紫式部。供養の布施を申し出る彼女に対し、法印は布施の代わりとして舞を所望する。
儚き世の理を見せる、式部の舞い姿。「その昔、数ならぬ身の私は石山観音さまの功徳を頼み、この寺に籠もって源氏物語を完成させました。しかし供養を怠ったことで、未だこの身は救われず…。法印さまにめぐり逢えた今、悟りへの道を願うばかりです」 彼女は自らの思いを巻物にしたため、法印に託す。
『――露のように儚き命。そんなこの身と向き合い、紫雲の来迎を願う日々。早く苦しみの世を船出して、悟りの岸へと辿り着きたいもの。迷いの雲は晴れやらず、栄耀栄華は定めなき小舟。願うは極楽の、蓮の花の台(うてな)ばかり。どうか阿弥陀さま、美辞麗句の罪にまみれたこの私を、西方世界へと救って下さいませ…』
式部は、自らの所願を舞に託し、後世を祈るのであった。
やがて空は白みはじめ、夢の夜は終わりを迎えようとしていた。「光源氏の供養を果たしたことで、私もまた、浄土へと生まれ変わることができます…」 式部は無常の世を観じ、ついに救いを得たのであった。
式部が見せた奇蹟の一夜。実は彼女こそ、この世の儚さを人々に伝えるべく現れた、石山観音の仮の姿。書き遺された言の葉、それは夢の世の物語なのであった――。
紫式部は『源氏物語』を書いた罪によって、死してなお救われぬ日々を送っている――。そんな内容をもった本作は、現代の感覚からすれば、荒唐無稽という印象すら受けるかもしれません。
能楽の成立した中世という時代は、仏教の全盛期でもありました。この仏教の価値観では「妄語」(偽りの言葉)は罪とされていますが、そうだとすれば、虚構の物語と美辞麗句とによって飾り立てられた〈文学〉の世界もまた、この「妄語」の罪に抵触してしまうのではないか――と、そうした葛藤が、〈文学〉をめぐる中世の人々の心にはありました。こうした、仏教的な罪とされた虚構や美辞麗句のことを、当時の言葉で「狂言綺語(きょうげんきぎょ)」と言い、本作でも上記「5」の場面で「狂言綺語をふり捨てて、紫式部が後の世を助け給へ」と謡われています。
そうした「狂言綺語」観において特に槍玉に挙げられたのが、本作にも取り上げられている『源氏物語』でした。能楽の成立した中世には、〈紫式部は『源氏物語』を書いた罪によって地獄に堕ちた〉とする理解があり、また〈『源氏物語』を目にする読者もまた地獄に堕ちることとなる〉と信じられていました。それゆえ、そんな罪深き『源氏物語』や紫式部を供養しようという営みが催されるに至り、そのことが物語の読者たちへの救済にもつながるのだと考えられていました。そうした文化現象の中で、本作の物語もまた成立したのでした。
このように、本来悪とされていた「狂言綺語」でしたが、そんな罪をも生みかねない〈ことば〉の力によって、かえって人々を救うことができるのではないか――と、そのような発想もまた、中世には盛んになりました。
こうした〈狂言綺語は本来罪悪だが、むしろそれを転じることによって、人々を救いへと導くことができるのだ〉という理念を体現するのが、「唱導(しょうどう)」の文学でした。唱導とは、たとえば法会の場において所願などを本尊に向かって述べたり、あるいは仏の教えを分かりやすく民衆に聞かせたりする文芸のことで、いわば〈ことば〉の力によって聴く者を仏道へといざなう営みでありました。そして、そうした晴れの場で活躍する文芸であるゆえ、唱導の作品は技巧的で美しい表現によって文章が綴られており、たとえば有名な『平家物語』の冒頭「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり…」の文句も唱導作品の引用であることが分かっています。現在でこそ文学史の中で顧みられることは少なくなってしまいましたが、この「唱導」の世界は、実は中世文学全体に多大な影響を及ぼした一大ジャンルだったのです。
この唱導の文筆を代々家業としたのが、本作のワキともなっている安居院(あぐい)の家でした。この家は、僧侶の身でありながら妻帯を許され、代々唱導の作家を輩出していった特殊な家系で、なかでも初代の澄憲や2代目の聖覚は名作家として知られています。この聖覚の作品に、五十四ある『源氏物語』の巻の名を織り込みながら救済への願いを表明した『源氏物語表白(ひょうびゃく)』という作品があり、この作品が、本作の上記「5」で謡われる〔クセ〕の典拠ともなっています。この『源氏物語表白』の成立をめぐっては、以下のような伝説が伝えられています(『源氏供養草子』)。
――あるとき聖覚のもとに、一人の若く美しい尼が訪れた。幼少のときから『源氏物語』を愛読していた彼女は、それゆえ仏門に入った今なお物語への執着を断てずにいたのだった。経巻を差し出す彼女。その経巻は、仏道に専念すべく、『源氏物語』を料紙にして書写したものであった。聖覚はこの経巻を供養してやることとし、その場で、物語の巻の名を織り込んだ『源氏物語表白』を書き上げたのであった。
実は彼女の正体は、関白近衛基実の娘・通子であった…。
本作は、このエピソードに着想を得つつも、ワキ・安居院法印のもとへ現れた女性を紫式部自身とし、また〔クセ〕で謡われる『源氏物語表白』の文章を聖覚ではなく紫式部自身がしたためた所願であるとしています。それによって、華麗な〈ことば〉の中に救済への願いを込めようとする式部の思いが、本作では描き出されているといえましょう。
(文:中野顕正)
過去に掲載された曲目解説「源氏供養」(文・江口文恵)
(最終更新:2017年9月)