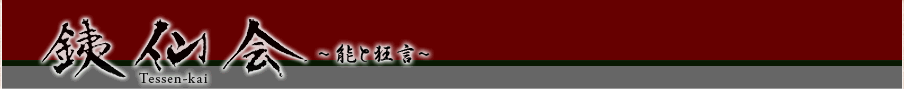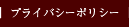小督(こごう)
◆登場人物
| シテ | 源仲国 |
|---|---|
| ツレ | 小督局(こごうのつぼね) |
| トモ | 小督局の侍女 |
| ワキ | 高倉天皇の勅使 |
| アイ | 隠れ家の女主人 |
◆場所
【1~2】
京都 源仲国の邸宅
【3~9】
京都西郊 嵯峨野 〈現在の京都市右京区嵯峨〉
概要
平安末期、平清盛の権勢に恐れて出奔した愛人・小督局への未練から、政務も手につかなくなっていた高倉天皇。天皇は局の在処を尋ねるべく、源仲国のもとへと勅使(ワキ)を派遣する。勅命を受け、恩賜の駒を賜った仲国(シテ)は、局が身を寄せていると噂の嵯峨野へと、駒を走らせ向かってゆく。
折しも八月十五夜。嵯峨野の民家に匿われていた小督局(ツレ)は琴を弾き、天皇を慕って『想夫恋』の楽を奏でていた。そこへやって来た仲国。かねて局の琴の音色を聞き覚えていた彼は、琴の音を便りに尋ねて来たのだった。天皇の手紙を渡す仲国へ、自らの想いを吐露する局。そんな彼女を慰めるべく仲国は酒宴を催し、局の思いに寄り添うと、彼女の言葉を天皇へ届けるべく、都へ帰ってゆくのだった。
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキが登場します。
平安末期。栄華の絶頂にいた平清盛は、皇室の外戚となって更なる権勢を得るべく、ついに娘の徳子を高倉天皇の中宮に据える。しかし目障りなのは、かねてから天皇の寵愛を受けていた小督局の存在。…そんな清盛の視線に危機感を覚えた局は内裏を出奔し、行方をくらましてしまう。その報せに深く悲しんだ天皇は、彼女の行方を尋ねるべく、勅使(ワキ)を源仲国のもとへ派遣するのだった。
2 ワキはシテを呼び出して勅命を伝え、シテは局を捜しに向かいます。(中入)
仲国(シテ)を呼び出し、局を捜し出して天皇の手紙を渡すよう命じる勅使。噂では、局が身を隠したのは嵯峨野の地、片折戸の民家だという。折しも今日は八月十五夜。琴に長けた局ならば、きっと月を眺めつつ琴を弾いているはず。そう考えた仲国は、琴の調べを便りに局を捜し出そうと約束する。色よい返事に、褒美の馬まで賜った仲国。彼は恩賜の馬に跨がると、そのまま嵯峨野の方へと出発してゆく。
3 ツレ・トモ・アイが登場し、ツレは身の不運を嘆きます。
その頃――。嵯峨野の里、とある民家の女主人(アイ)のもとに匿われていた、小督局(ツレ)と侍女(トモ)。かりそめの寓居とはいいながら、賤の女たちの中で日数は次第に積もりゆく。徒然の心を慰めるべく、遣る方なき思いを託して琴を弾きはじめた彼女。その音色は折からの秋風に響きあい、虫たちまでもが音を添える。枯れゆく秋の心に沁みわたる、天皇への思い。局は、儚い恋の愁いを胸に、琴を弾き続けるのだった。
4 シテが再登場し、秋の風情の中で局の寓居を捜します(〔駒之段〕)。
そこへやって来た仲国(シテ)。十五夜の月の下、彼は恩賜の駒を馳せ、局の寓居を尋ねゆく。片折戸の賤家を一軒ずつ巡っては、耳を澄まして佇む仲国。もしやと思い、彼は法輪の地へと向かう。すると幽かに聞こえてきた、峰の嵐や松風にまがう琴の調べ。それは紛れもない、局の音色。奏でる曲は『想夫恋』。“夫を想う恋”の曲こそ、天皇を慕う局の心に他ならぬ。そんな局の想いを知り、仲国は喜びつつ向かってゆくのだった。
5 シテは局の寓居を訪れます。
案内を請う仲国へ、門違いではと答える局。しかしかつて殿上の管絃に笛の役を勤めていた彼は、局の音色をしっかりと覚えていた。人目をつつむ涙までもがあらわれた、今の調べ。在りし昔の十五夜の遊宴に変わらぬ、月光の下の今日の宵。
寂しげな嵯峨野の古道を辿るのも、君の恵みに洩れぬしるし。所を隔ててなお互いを思いあう、変わることなき天皇と局の想いなのであった。
6 シテはツレと対面し、天皇の手紙を渡します。
露に萎れて佇む仲国の姿に、遂に対面を許した局。仲国は、天皇の落胆の程を明かし、預かってきた手紙を局に手渡すと、局自身の口から返事の言葉を賜りたいと願い出る。及びなき身ながらも、これほどまでに愛された局。彼女はそんな天皇の思いに感謝し、真心のこもった筆跡を見つめて涙するのだった。
7 ツレは、天皇への思いを述べて詠嘆します(〔クセ〕)。
――昔、李夫人の面影を慕う反魂香の煙は武帝の夜の物思いとなり、楊貴妃を偲ぶ玄宗の思いは風の音信となって愛の言葉を世に遺した。愛する人の亡き跡を追い求め、弥増しに恋の想いを募らせゆく、君の心の哀れさ。しかし同じ世に生きてさえいれば、たとえ離れ離れになろうとも、また逢う頼みもあるというもの。都の外のこの山里までも心にかけて下さる、天皇の思いの有難いこと…。
8 シテは、名残りの酒宴に〔男舞〕を舞います。
局自身の返事を聞き、都へ帰ってゆこうとする仲国。対面ももうこれ限りと、局は彼の後ろ姿を慕って涙する。そんな彼女に、仲国は告げる。今は離れていようとも、いつの日か、再び天皇と会える日はやって来るはず。その暁には、すぐさま迎えの車を立てましょう――。そう慰める彼の言葉にも、局の嘆きは止むことを知らない。名残りの酒宴を開く仲国。名月の夜、彼は音楽の響きに舞の興を添え、局の心に寄り添うのだった。
9 ツレは、去ってゆくシテを見送ります。(終)
近づいてきた別れの時刻。引き留める言葉も見当たらぬ、局の嘆き。天皇と局、愛しあいながらも想いの叶うことなき二人の運命に、仲国までもが涙する。しかし、嘆きに沈む天皇へ、局の言葉を伝えることは叶った。この嬉しさを胸に、彼は駒に乗って帰ってゆく。そんな仲国の後ろ姿を、局はいつまでも見送るのだった――。