■2018年09月14日 定期公演 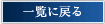
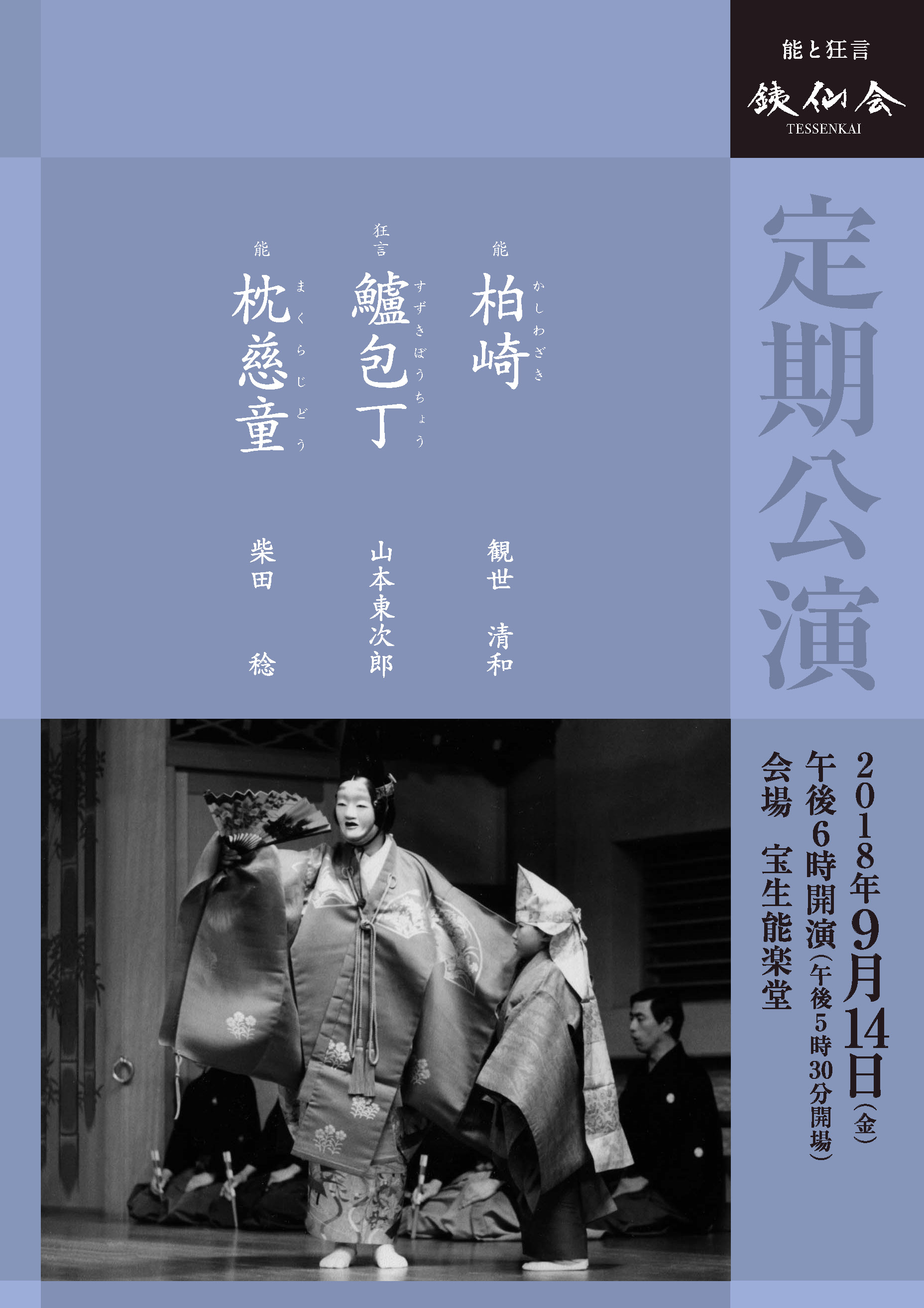
能 柏崎
| 前シテ 後シテ |
花若ノ母 狂女 |
観世 清和 |
| 子方 | 花若 | 谷本 康介 |
| ワキ | 小太郎 | 森 常好 |
| ワキツレ | 善光寺住僧 | 舘田 善博 |
| 笛 | 一噌 庸二 | |
| 小鼓 | 観世新九郎 | |
| 大鼓 | 亀井 広忠 | |
| 地謡 | 安藤 貴康 長山 桂三 北浪 貴裕 小早川 修 |
西村 高夫 浅見 真州 観世銕之丞 清水 寛二 |
| 後見 | 野村 四郎 | |
| 谷本 健吾 |
越後の柏崎殿は訴訟のため、子の花若とともに鎌倉に滞在していたが、風邪を患い程なくして死してしまう。さらに花若も父の死を嘆いて出家し、行方知れず。家臣の小太郎は柏崎殿の形見と花若の文を花若の母に届け、夫と子の二重の悲報を伝える。
花若の母は悲しみゆえに物狂いとなり、柏崎を出て信濃国善光寺へとやってきた。御堂の内陣は女人禁制と咎められるも狂女は反論し仏前に進み出る。夫の極楽往生を祈り念仏を唱えると、夫の形見を身に纏い、舞を舞う。そして、折しもそこへ参詣していた僧形の花若が現れ、二人は再会を喜ぶのであった。
阿弥陀浄土の地善光寺を舞台に、さまよう狂女の能。
さらに詳しい解説は<こちら>から
———————〈休憩10分〉———————
狂言 鱸包丁
| シテ | 伯父 | 山本東次郎 |
| アド | 甥 | 山本 則孝 |
淀に住む甥は、都の伯父が仕官したので、その祝宴用に鯉を求めてくるよう言われているにもかかわらず未だ求めていない。そこで甥は、求めた鯉を川中に放っておいたところ獺に片身を食べられてしまったと嘘をつく。甥の嘘を見抜いた伯父は、よくよくもてなしてやろうと、まずは打ち身(刺身)の謂れを物語り…。
能 枕慈童
| シテ | 慈童 | 柴田 稔 |
| ワキ | 勅使 | 村瀬 提 |
| ワキツレ | 従者 | 福王 和幸 |
| 〃 | 〃 | 矢野 昌平 |
| 笛 | 寺井 宏明 | |
| 小鼓 | 亀井 俊一 | |
| 大鼓 | 亀井 実 | |
| 太鼓 | 小寺眞佐人 | |
| 地謡 | 鵜澤 光 観世 淳夫 青木 健一 谷本 健吾 |
長山 桂三 馬野 正基 浅見 慈一 北浪 貴裕 |
| 後見 | 浅井 文義 | |
| 泉 雅一郎 |
漢の皇帝の命により、勅使はれっけん山に流れる薬の水の水源を求めに山中に着くと、菊に埋もれた一軒の庵を見つけ、中に住む美しい慈童と出会う。
聞くと慈童は八〇〇歳、周の代に仕えていた者で、昔誤って帝の枕を跨いでしまったためこの山に遷されたのだという。しかし憐れんだ帝より妙文が示された枕を授かり、その妙文を菊の葉に書き写して水に浮かべると、水はたちまち薬の水となって不老長寿を保ち、今までこうして暮らしているのだと語る。そうして慈童は仙楽を奏でて楽を舞い勅使一行をもてなし、薬の水を勅使に捧げ、長寿を祝福するのであった。
清澄な深山で繰り広げられる、明るく朗らかな能。













