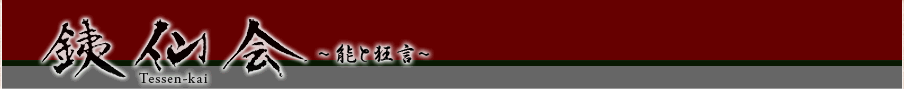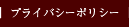百歳の老女となった小野小町を慰問すべく、新大納言行家(ワキ)が陽成院の和歌をたずさえ近江国関寺を訪れると、都での物乞いを終えた小町(シテ)が帰ってきた。小町から今の暮らしぶりを聞いた行家は、帝の歌を彼女に伝える。老い衰え、歌を詠む気力も枯れていた小町だったが、せっかくの帝の厚意に応えるべく“鸚鵡返し”の古法によって返歌をすると、行家に歌の道を語る。そうするうち、歌人として一世を風靡していた往時の栄華を懐かしんだ彼女は、かつて見た在原業平の輝かしい舞い姿を追憶し、その面影を慕って舞を舞いはじめる。やがて夕暮れ時、帰ってゆく行家の後ろ姿を見送ると、小町は静かに庵へ帰ってゆくのだった。
|
作者 |
未詳 |
|
場所 |
近江国 関寺の傍ら (現在の滋賀県大津市逢坂) |
|
季節 |
不定 |
|
分類 |
|
シテ |
百歳の小野小町 |
面:姥など 壺折腰巻女または水衣姥出立(老女の道中姿の扮装) |
|
ワキ |
新大納言行家 |
風折狩衣大口出立(男性貴族の扮装) |
概要
ストーリーと舞台の流れ
1 ワキが登場します。
平安時代。時の帝・陽成院は和歌の道を愛し、世に栄える歌の数々を選び集めようと思い立つ。ところが、その肝心の名歌がなかなか集まらない。そんなとき帝が思い出したのが、かつて一世を風靡した大歌人・小野小町の存在であった。聞けば彼女は、百歳となった今なお存命であるという。帝は、彼女を慰問する歌を新大納言行家(ワキ)に託すと、彼女の暮らしているという近江国関寺へ向かわせるのだった。
2 シテが登場します。
その頃――。都から近江への道をとぼとぼと歩む、一人の老女がいた。やつれきった面ざしで杖にすがる彼女こそ、今や百歳となった小野小町(シテ)。長い人生の果てに感傷の思いを深めた彼女は、世間から狂人と呼ばれつつ、日々を送っていたのだった。
逢坂山の峠に立てば、眼下には青々と広がる琵琶湖の光景。そんな近江路を、彼女はひとり歩みゆく。
3 ワキはシテと言葉を交わします。
庵へと帰ってきた小町。声をかける行家に、小町は、こうして関寺のほとりで過ごす今の暮らしを明かす。「閑居には趣ある、この関寺の地。庵の前には人々の行き交う街道がのび、後ろからは霊山が包み込んでくれる。花かと見まがう白雲の春、そんな深山の春の香を、松風が枕元へと運んでくる。北には湖が広がり、東は石山寺や瀬田の長橋。そんなこの地こそ、老い果てたこの身にとっての、終(つい)の棲家なのです…」。
4 ワキは帝の和歌をシテに伝えます。
毎日都まで足を運び、物乞いをして暮らす彼女。宮廷社会に生き、歌を嗜んでいたのも、遠い過去のこと。そんな小町に、行家は帝の歌を手渡す。老残の今の望外の喜びに、さっそく取り上げた小町だったが、既に目は霞み、字を読むことすらできぬ身となっていた。
そんな彼女のため、読み聞かせる行家。『雲の上は在りし昔に変はらねど 見し玉簾の内やゆかしき』――それは、“宮廷は今も恋しいか”と尋ねる、ねぎらいの言葉であった。
5 シテは“鸚鵡返し”の技法によって返歌をします。
世に忘れ去られたこの身へと語りかける帝の歌に、静かに聞き入る小町。年老い、歌を詠む気力も枯れてしまった彼女だったが、せっかくのこの歌に応えるべく、『ぞ』の一字で返歌をしようと言う。『内やゆかしき』から『内ぞゆかしき』へ。「これこそ、歌道の古法“鸚鵡返し”。帝の歌を盗用するようで畏れ多い事ながら、これも歌の道、どうかお許し下さいませ。思えば、こうしてお言葉を頂けるのも、全ては歌道のお蔭なのですね…」。
6 シテは歌道の徳を語りつつ昔を思い出し、今の身を嘆きます(〔クセ〕)。
歌の道を語る小町。そんな彼女の心には、華やかなりし日々の記憶が次第に蘇ってきた。“ただ弱々と詠む”と評された歌風にも違わぬ、儚い追憶に生きる彼女の心。「歌の模範とされたうえ、絶世の美女と謳われ、最高の栄誉をほしいままにしたかつての私。雨に濡れた桃花、風に靡く柳のごとき、あの輝かしいわが身の日々。――しかしそれも昔のこと。今ここにいるのは、げっそりと痩せ落ちぶれた、一人の醜悪な老女の姿…」。
7 シテは烏帽子・長絹を身につけ、舞を舞います。
追憶に身を委ねようとする小町。彼女は行家に促されるまま舞の装束を身につけると、かつて見た在原業平の舞の記憶を語りはじめる。「業平さまが玉津島明神へ舞を捧げると聞き、私はその姿を一目見ようと、夜の都を出発して玉津島へと向かいました。麗しい装束を身にまとい、神前で舞の袖を翻す業平さまは、まるで光輝く珠玉のよう…」 それは、長い彼女の人生の中でも、最も慕わしい記憶のひととき。もしも、あの時に戻れるなら――。舞の袖をじっと見つめていた小町は、やがてゆったりと、懐旧の舞を舞うのだった。
8 シテは昔を偲びつつ嘆き、やがて去ってゆくワキを見送ります。(終)
「――そんな日々も、遥かの昔となってしまいました。瞬く間に過ぎてゆく過去。光陰とは、こんなにも速いものだったのですね…!」 ついに感極まった小町。彼女は、長すぎた人生を思って涙するのだった。
やがて別れの時刻。都の方、沈みゆく夕陽に向かって、行家は去ってゆく。その背中を静かに見送ると、小町はひとり、庵へと帰っていったのだった――。
(文:中野顕正)